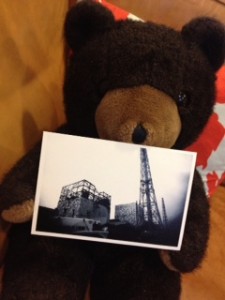今日のできごと
小原一真 福島 写真展
2013年04月01日今日のできごと
「アンナ・カレーニナ」鑑賞後、カメラマン 小原一真さんの写真展に伺った。
小原一真さんは、京都で写真展「原発作業の肖像」で、その作品と志に触れ、大きな衝撃を受けた。
(詳しくは http://yukayoshimi.com/contents/article.php?id=1078 参照)
Facebook等で、小原さんのその後の活動は気に留めていたのだが、
今回、東京 に於いて写真展を行うというので、在廊する時間を見計らって、渋谷まで足を運んだ。
PARCOの奥の店舗スペースに並べられた写真。
門外漢の私は、写真の良し悪しは、正直、よくわからない。
ただ、小原さんの写真は、キャプションというのだろうか、短い説明書きと共に、確実にエモーショナルなのだ。
世界報道写真展によく見る海外の新聞の一面を飾るような、一目で、見る者にインパクトを与えるようなセンセーショナルな写真とは、またジャンルが違って、
静かに一瞬を切り取った写真。
そこに、簡単に添えられた短文が絡み合って、静かな波動となって、体内を揺さぶるのだ。
静かに、ゆっくり、確実に。
今回は、あの日から二年を迎えた被災地に対して、自分自身の向き合い方を改めて考え、撮影した写真が並んだ。
今回、初めて手にしたという、ハッセルブラッドで撮影された温かみを感じる、ポートレート。
だからだろうか。
彼らの真正面に立つと、被災直後の恐怖や怒り、切羽詰まった空気とは、ちょっと違った少し緩んだ心を感じた。
でも、その弛緩は、きっと諦めにつながっているのだろう。達観というか、目の前に広がる圧倒的に無慈悲な事実。
どう頑張っても覆しようない、残酷な現実。
受け入れ、それに流され、背負っていくしかない日常。孤独。
切なさ、やり切れなさが、画面以上の大きさを以って、迫ってくる。
その中で印象的だったのは、
福島の中学生の女の子のことば。
「どんな大人になりたい?」
彼女は「責任を押し付け合うオトナにはなりたくない」
小原さんから京都で聴いたお話の最後のくだりを思い出した。
「自然エネルギーになろうと、発送電分離になろうと、結局は社会が変わらないと、なんの問題解決にもならないんです。」
今、日本に広がる偏った社会システム。そこに根付くニンゲンの思考・行動パターン。
そこを、変えなければ、正さなければ、結局、同じ事の繰り返しなのだ。
その根本が、先の彼女の発言「責任を押し付け合うオトナ」なのだ。
先ごろ、誰も何の責任も取らない、という状況に遭遇した。
どれだけもがこうと、叫ぼうと、どうしようもない、絶望感。
唯一、私を支えた事は、寄り添ってくれる人の存在であり、言葉だった。
大きな流れには、流されるしか方法はない。
それは、時には仕方ない。
社会なんて、そんなものだ。
そこに呑まれないようにするには、その中で、しっかりと自分の足で立っていられるためには、寄り添ってくれる人の存在と言葉が、何より大切だった。
だから、忘れない。
こんなちっぽけな自分に、何もできる事はない。
でも、私は寄り添ってくれる存在が、どれだけ大きいかを知っている。
これしか出来ないけども、それさえも出来ない自分にはなりたくない。
もちろん、福島の問題以外でも。
日本が原発を輸出するベトナムの写真等を拝見して、色々お話を伺ったあと、「頑張ってください」と小原さんと握手を交わして、その場を後にした。
Twitterにしたためた言葉は「小原さんの追っている問題は、軸をずらせば、我々のすぐそばに、どこにでもある問題だ」。
同じ事象をどう切るか。
その視線が重要だ。
小原さんの立脚点はとても説得力に溢れている。
小原さん撮影。あげて大丈夫かな?
ぶれちゃったけど。展示スペースの片隅におかれていた、小原さんの相棒。
「一日の終わりに」
2013年02月22日今日のできごと
この曲、身体が震える。
今日は、夜から、歌唱のレッスンに行ってきました。
わがままを言って、ある曲のお稽古を先生にお願いしました。
それは「一日の終わりに」。
大好きなミュージカル、「レ•ミゼラブル」から。
映画をご覧になった方、フォンティーヌを始め、ファクトリーガールが工場で、揃いの青い衣装で、歌うあの曲です。
あれは、英語で聞いてもリズムと滑舌がむつかしいのですが、その曲が持つ難易度プラス、日本語になると、翻訳詞独特の難しさもあり、これが、ちょーーー難しい。
ほんと、歌になる以前。
初心者のわたしなんぞ、声が出来てないから余計に。
実は、この曲は、私が「表現する」って事をもう一度やりたい、と思った原点の曲なのです。
以前、宝塚の元トップスターの先生に一ヶ月だけ、歌唱を習ったことがあります。
そこで、課題とされた二曲のうちの一曲が、この曲。
初心者が歌う、歌える曲ではありませんが、全く。
音とリズムを取るのが必死(でも結局とれてない)な私に、
ピアノを弾きながら、先生は、さすが、元娘役トップスターらしい可憐な声で「もっと怒って!」「もっと!」「もっと!」と煽るのです。
楽譜に落とされた作曲家の意図に合わせて、自分の感情をコントロールする。
あ、歌って芝居なんだ、と気付いた瞬間でした。
なんていうんだろう。
「ガラスの仮面」で、北島マヤが、トキを演じて、嫌がらせで差し替えられた泥まんじゅうを食べた時の様。
(わからんよね‥この例え)
説明のつかない感情が、身体を支配するのです。
そんな経験をした曲でした。
ミュージカル「レ•ミゼラブル」は暗くて救いのない群衆劇で、
この歌は、先生によると、かなり芝居っ気の必要なナンバーらしいです。
先生も、この曲を歌うと疲れるとおっしゃっていました。
全身汗をかいて、お稽古を終わり、スタジオを出た途端、
身体が震えてきました。
さすが、の先生のお手本。
自分の内面をコントロールする、
感情の再生産。
疲れるけど、ストレスが全部なくなるかのような爽快感も。
先日、竹中直人さんが「僕のストレス解消法は、芝居です。感情を全て発散させるから」と、インタビューで答えて下さいましたが、納得。
自ら商業演劇のプロデュースもする先輩が「磨り減った感情を、芝居を観る事で蘇らせた」とおっしゃっていましたが、それと同じ感覚。
楽曲が持つパワーと、先生の渾身のお手本。
音楽の持つエネルギーにあてられ、ふらふらになりました。
この曲を歌うと、なんでもう一度、表現することをやりたいのかを再認識できるのです。
ああ、うまくなりたいな。
ひとの感情を動かせる様な歌を、歌える様になりたいな。
まぁ、本業のナレーションでも良いんだけれども、ね。
いよいよ公開 “レミゼラブル”
いよいよです。
最近テレビから流れるあるメロディーに、私がキョドウフシンになる現象が続いていました。
これです。「レミゼラブル」です。

この新ブログでも一度お話した事があると思うのですが、私は「レミゼラブル」のミュージカルがなにより好きです。
(旧ブログにも何度か書いてるかな?)
聞くだけで、無条件で涙です。
15歳の時、初めて見たこのミュージカル。今や総観劇回数はわかりません。
今、冷静に考えてみると、なんで若い頃に、この舞台に出たい!と、真剣に歌と芝居をやらなかったのか、なんと無駄に時間を過ごした事か、と悔やまれて悔やまれてなりません。
まあ、芝居は天才の存在を知って諦めたのですから、再び芝居を!と思わないはしかたないか。
その大好きなミュージカルが、映画になります。しかも最高のキャストとスタッフで。
表参道の駅に、音楽つきで展開されてました。
人を訪ねて伺ったAoビルの最寄りの出口に展開されていたことも、レミと相性がいい証拠(?)。
この前で、有に10分。佇んでしまいました。歌ってました。そして、泣いてました。
おそろしくいい作品です。
今日から公開。一人でも多くの人に見に行ってもらいたい。
私は、、、いつ行こうかな。
好きなものは最後に食べたいタイプ、、、見たい、見たくない、見たい、見たい!!!ああー、悩むー。
おめでとうございます!
今日は、お仕事ではなく、結婚式の司会へ。
お天気が心配されていたのですが、晴れて良かった!
今日の新郎新婦さんは、実は、東京に来て、とてもお世話になった方なんです。
「結婚が決まる前から、披露宴するんだったら、吉見さんに司会してもらいたいなー、と思っていたんです」とお声がけいただきました。
こういう時、本当に嬉しい。
今まで、色々なこともありつつ、700組以上も披露宴のお仕事を頑張ってきたかいがあります。
お二人が選ばれた会場は、一軒家パーティースペース。
披露宴の時間も、2時間程度とコンパクト。
特に余興とかスピーチとかを入れ込まず、ゆっくりお食事と歓談でお楽しみいただくスタイルで、
お二人らしいゆったりとした時間が流れました。
ご新婦の本当に嬉しそうな笑顔が印象的で、その新婦をしっかりと見守るご新郎。
ああ、いいご夫婦だなー、と実感しました。
年齢柄?、もうお友達の結婚式で、司会をすることはないかなー、なんて思っていたのですが、
幸せのおすそ分けをいただきました。
いついつまでもお幸せに!!

酉の市 デビュー!
2012年11月20日今日のできごと
酉の市。
関西人には、全く馴染みがありません。
関西人は、年明けのえべっさんですから。
東京に来て、新宿に住んでいた時、花園神社の賑わいに???
と思っていました。
番組で、峰さんが毎年酉の市にいてらっしゃる、と聞いて、帰り道、行ってきました。
目黒 大鳥神社。
こじんまりとした感じですが、
境内に縁起物屋さんが並び、威勢のいい声が響きます。
あぁ、ニュースでみたー。
一の酉の日、Twitterで、有吉さんが後輩芸人に「熊手は徐々に大きくするもんだよ」と助言され、その風習を知ったわたし。
大阪から引っ越して来て、河岸を変えて、お仕事している訳ですから、郷に入っては郷に従え、で、私も熊手を購入しました。
本当に小さいの。
まあ、これからどんどんおおきくなりますように。
来年は、社会全体、今よりちょっとでも前に進めばいいですね。
良いお年を(ちょっと早い)