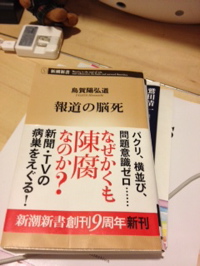烏賀陽弘道氏の「報道の脳死」を読了した。
この一冊に関しては、一般の読者諸氏とはちょっと違った感想を持ったかもしれない。
あえて、駆け出し局アナだった15年前の私を登場させてみよう。
その彼女の感想は「何があかんの?」
そうだ。
この本の第1章から第3章までに描かれてるのは、新卒で勤務した放送局で、
また、フリーになってからの地元報道を旨とするケーブルテレビで働いてきた時、数えきれないほどみてきた光景だ。
報道部のデスクの前のカレンダーに記された◯周年の文字、
記事を入れる書類棚に入った、定型の予定稿。
原稿に手を入れ、キューシートを書くデスクの茶色いネクタイや、デスクが使っていた黄色い鉛筆や定規まで、鮮明に思い出される。
(しかも◯月◯日解除と朱書きしている原稿を、気付かずにニュースに乗せてしまった、笑えない希有な経験まで持ってますというおまけ付きだ。)
本当に、本当に、この本に書かれている事はメディアのニンゲンにとって、日常の一コマでしかないのだ。
就職活動時、私は放送局を志した。
その理由のひとつは
「知りたかったから。または伝えたかったから」。
当時、岐路に立った時、なにか決断を迫られた時、
多くのモノごとを若いなりに、自分なりに決定してきた。
その時、一番大切にしたことが “多くの事実を集める” と言う事だった。
その事実を組み立て、自分なりの決断を下す。
「知る事」こそ、ニンゲンの行動の第一歩だと考えていた。
だからこそ、知りたかった。
多くの情報にアクセスして、それを多くの人に分かりやすく伝えたかった。
当時、マスコミは新聞か放送かの二極時代。
情報伝達というメディアシステムの中で、
一番ニンゲンの体温を以て、より複合的な伝わり方をする手段として放送局を選び(まあ、新聞社を志望するだけの根性と知性と文章力がなかったのも大きいが)、
幸運にも、アナウンサーとしてメディアの一員になることができた。
「国民の知る権利の代理者」なんて綺麗なことばでは語れなかったけど、
知りたい、伝えたいという思いを以て取材や番組に臨んでいたのなら、
ここに定義されている「ジャーナリズム」の一項が立派に?当てはまっている。
しかし、この本を読み進めるうちに、怖くなった。
そんな立場にいた私が、きちんと3大原則(客観、公平、独立)をまもっていただろうか。
今から思い起こしてみても、誘惑はそこかしこにごろごろしていた。
新人ちゃんの周囲にも。それが、一線を越えてしまう事の自覚もなしに。
でも、取材は恐ろしい。
どこの立ち位置から、またどんな結論に向かって、拾い集めた素材を編集するかによって、全くその出来上がりが違う。
与える印象も全く違う。
極論、最後には、軸となるのは自分自身の心持ちしかない。
そこまでの強い気持ち、根気強さ、自信と表裏一体の柔軟さを持ち合わせていたか。
きっと、この本にでてくる色々な問題点は、もしかしたら報道だけの問題ではなく、ニッポン全体の病巣なのかもしれない。
ひとつ例に挙げよう。「断片化」。
以前、割れるほどの頭痛を抱え、深夜の救急病院を始め、何度も何度も泣きながら病院にかけこんだ。
ドクターは「原因不明です」「様子見るしかないですね」とだけ繰り返す。
点の診断でしかないのだ。
コチラの正直な感想は「で、どうなの?」
今、ひとりのニンゲンが、かなりの痛みを訴えている。
その目の前の現実に対して、誰も統合的な判断をしてくれないのだ。
パーツをくみ上げて、シロウトが必死になって全体像を想像するしかなかった。
本当に、失望した。痛いのに。
報道だけでなく、医学だけでなく、きっとそういう視点は、現在のニッポンの社会全体に欠けているのだろう。
この本は、強力な分析本だ。
よくぞここまでと言う思いと(ほら、嫌コトですからね、内部からは。でも、誰かが言わなきゃね)、
そうそう、それが言いたかった、という思いと。
立場が変われば意見も変わる。
現在進行形のメディアの病理について、「至極ごもっともで、、、」と額をたたいてうなづき、恥入るしか為す術がない。
だから、正直、感想なんてないのだ。
経費削減の現場から「無難になるしかないんです!」とつぶやく現職記者の声がかすかに聞こえるようだが、
じゃ、あなたはどうして記者を志したのですか?
あなたのやりたかった事はなんですか?
入社当時の志望動機を、もう一度話してくれますか?と質問されると、
もうどうしようもない。
困ったことだ。
そうそう、著作全体の感想ではないが、
特に共感を覚える点を。
キャリア形成において、初期教育の大切さ、だ。
私が、KBS京都という関西ではちょっと知られた異色放送局に就職をして、一番良かった事は、
「放送人としての初期教育を徹底されたこと」だ。
これは、どれだけ感謝しても、本当に足りない。
先日、ある放送業界の方に、
「地方の元局アナって信じないんだよ。上がいなかったり、現場主義だったりで、全く基礎がなってないコトが多いからね」と冷たい目で言われたが、
その後のことばで、私に関してはその件はどうやらクリアできたらしい事を知った。逆に驚かれた。
イトマン事件で有名になる前、KBS京都が一番きらきらしていた頃活躍していた敏腕個性派ディレクター達の薫陶を受けた、最後の世代だと自負している。
女子大出身の世間知らずの生意気なあほちゃんを、
一応、フリーランスでも、しゃべりで飯を食えるまでに仕立ててくれたのは、他ならぬKBSの先輩方だ。
この点は、氏が朝日で経験されたことと、多いに重なって見える。
(大朝日と比べて恐縮です)。
非常に納得。
仲間を見つけたようで、なんだか嬉しくなる。
さて、一体この本は、誰が読むべきなんだろう。
ジャーナリスト志望の学生さんか?
(まだ実感はないかも。。。)
情報の受け手である(従来的な用法での)市民か?
(メディアを、誹謗中傷するだけの材料にはされたくない。絶対に)
やっぱり、現職(ジャーナリストだけではなく、メディアに関わるもの全般)しかいないだろう。
自浄作用はもう期待されていないけど、
とにかく、客観的に自分の立ち位置を確認する必要はあるだろう。
まあ、会社員ですから、の一言で済まされると、何も言えないけど。
そうそう。一応、私も現職でした。
新聞社から配信されてくる原稿を選別し、
尺の中で構成を考え、時にはリライトし、文章を切り貼りし、
ラジオというメディアを通して、原稿を音声に変え、聴取者に届けるという報道の仕事をしている。
テレビであれ、ラジオであれ、
私は、大学生の春に、ここで生きていきたいと思った。
あの頃のきらめきはもうとっくに感じないけれど、
飽きっぽい私が「メディアの中で生きていくこと」だけは、捨てていない。
だから、もう少し、ここで頑張りたいのだ。
例え、時代遅れで、死に体のオールドメディアであったとしても。
良くも悪くも、ニンゲンの体温を以て伝えられる、
厳しさと強さと覚悟ももっている、
そして(世代でくくるのはもうナンセンスだけれども)、
世の中の潮流から取り残されがちな30代、40代の女性にも取っ付きやすい情報の入り口であるように。
しゃべって、しゃべって、しゃべり倒したいのだ。
そんな自分の理想の仕事像をもう一度整理し、
もうちょっとだけ、ここでがんばるのだ、なんて思いに駆られている。